ブランクを超え、新たな挑戦へ踏み出すアナタへ。
10年間、家族を守り続けた専業主婦が社会に出る___。
札幌市内の小学校で特別支援学級主任を務める藤本さんは、かつて「専業主婦」として家事・育児・家計管理を背負い、不安と葛藤しながら日々を過ごしていた。
22歳で結婚。
23歳で出産。
そして10年間の専業主婦を経て、再び社会へと踏み出した。
明るい笑顔とバイタリティにあふれる彼女の歩みの裏には、“家族を守る”という強い責任感と、もし自分が倒れたら…という危機感があった。
この記事は、新たな挑戦へと一歩踏み出す人に届ける、専業主婦のリアルストーリーである。

専業主婦という“見えない存在”が担う主婦業
「専業主婦って目に見えないのさ。でも、すごい仕事なの。だから私は“主婦業”って言ってたの。すごいから。」
藤本さんの地元は、北海道東部にあるオホーツク圏の中核都市・北見市。
日本一の玉ねぎ生産地として知られ、夏は35℃、冬はマイナス20℃と寒暖差の激しい場所だ。
短大を卒業後、道東の高校で実習助手として働くかたわら、自然の家でボランティア活動をしたり、児童館で子どもたちと関わる日々を送っていた。
その後、22歳で結婚。
24歳で長男を出産。
以降、10年間にわたり専業主婦として家庭を支えてきた。
「専業主婦も結構こってりしていた。私の中では。」
「専業主婦って目に見えないし。」
「専業主婦がんばってます!って言う専業主婦ってあんまりいないの。」
家事・育児・家計管理。
すべてを担う日々は、社会から評価されにくい一方、数字に換算できない大きな重責だった。藤本さん自身も「圧迫感・切迫感がすごく嫌で、家計管理をしっかりしないといけないって思って…。」と振り返る。
そんなある日、子どもと訪れた図書館で偶然“家計簿講習会”を見つける。羽仁もと子さん(日本人初の女性ジャーナリスト、教育思想家)が設立した、友の会主催の講習に「何じゃこれ!めっちゃ気になる!」とすぐに予約したと言う。
そこでは、家計簿のつけ方やライフイベントに備えたお金の考え方を学べただけでなく、講師である先輩主婦たちが謙虚に、優しく寄り添ってくれた。
「涙が出てきちゃう…。」
藤本さんにとってそれは、“見えない存在”として不安に立ち向かっていた自分が、確かに認められたと感じられた瞬間だったのかもしれない。
その後、パートナーの仕事の関係で転勤が決まり暮らしは一変する。
北見から札幌へ___。
いよいよ、藤本さんに“働く”という選択が迫られることになる。
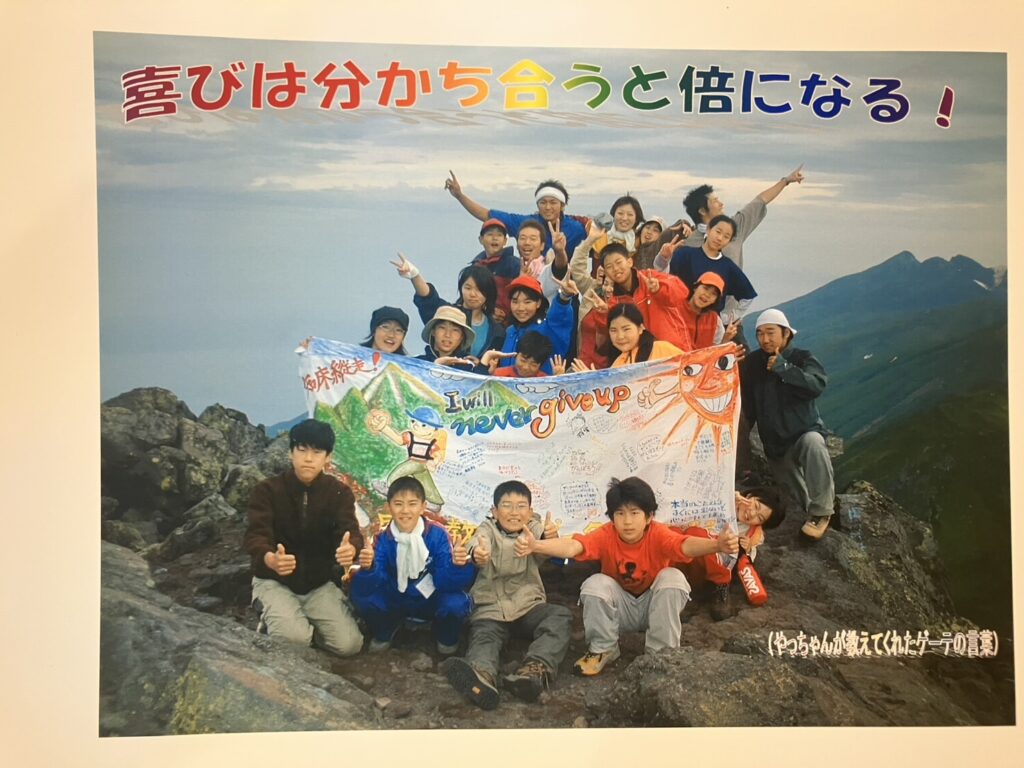
きっかけはインフルエンザ|主婦業10年で感じた家族への危機感
パートナーの転勤が決まり、藤本さんは北見から札幌へと移り住んだ。
人口は20倍近い。
暮らしは大きく変化した。
行きたい場所も増え、欲しいものも多くなった。
「お菓子を毎月5,000円くらいの予算にしてたの。でも、めっちゃ微々たる金額なの。足りないの。」
「こんなせこまか家計管理してても、『イヤイヤ、働いたほうが早くね!?』っていう感じになったの。」
節約の限界を感じて、与えられた範囲を広げないと苦しいと強く思い、働くことを決意したと言う。
だが、その決意の裏にはもう1つのストーリーがあった。
藤本さんは少し笑顔を見せながらも、どこか寂しい表情で切なくも見えた。そして、「ちょっと違う視点になっちゃうんだけど。」と前置いて、話を続けた。
「私が急に病気になったりとかして死んだりしたら、この家族崩壊すると思ったの。」
娘が幼稚園の頃、インフルエンザで40度近い熱を出したことがあった。
普段は健康管理に気を遣い、風邪ひとつ引かなかった藤本さんにとって大きな出来事だった。
「ごめん!作れない!ご飯買ってきて!」
そうパートナーに頼んだ夜、家族の夕食はすべて買って済ませることになった。
その金額は、必死に節約してきた家計にとって大きな衝撃だった。
「めっちゃやりくりしてたのに。みんな死んじゃうし、家計やりくりできないと思った。」
翌朝、まだ熱の下がらない体で弁当を作っていた自分を思い出し、このままではいけないと強く感じたという。
行きたい場所や欲しいもの、子どもに習い事をさせたい気持ち。もちろんそれも働く動機にはなり得た。だが本当の理由は、もっと切実だった。
「働こうと思った。みんなの自立が目標だった。」
そう語る藤本さんの言葉には、当時の不安や覚悟が入り混じっていた。
この出来事をきっかけに、“見えない存在”だった藤本さんは、10年ぶりに「働く」という一歩を決意し、“見える存在”へと変わっていった。

求められることの喜び___“見える存在”へと変わった
決意した藤本さんは、まずハローワークに向かった。
主婦業10年。
働き方はもちろん、面接の仕方もわからない。
そんな不安とは裏腹に、担当者は経歴を見て「めっちゃいいじゃん!」と背中を押してくれ、すぐに求人を紹介してくれた。
面接指導も受け、無事10年ぶりの就職が決まった。
「新鮮だし新しいことだったから楽しくはあったけど、覚えることが多かった。」
「それに、家事との両立をしないといけない。(主婦業が)なくなるわけじゃないから。」
仕事と主婦業の両立は厳しかった。
それでも“求められている”、“社会の中で役割がある”という実感は大きなやりがいとなった。
体力的には厳しかったが、経済的にも余裕が生まれた。
1年の契約を終えた後も「すごい楽しかったし、自分で頑張ってきた社会人としての生活は崩したくないと思ってたから。」と再びハローワークへ。
次の仕事も無事決まった。しかし、今度は1ヶ月の契約。
「エンジンがずっとかかってたから、お仕事もフリーになって手持ち無沙汰になった。」と振り返る。
その後、学校の校務助手の仕事に応募するも教育委員会から連絡が来ない。いても立ってもいられない気持ちになって再度問い合わせたところ、こう聞かれた。
「教員免許は何を持っているんですか?」
短大時代に取得していた家庭科の教員免許が、思いがけない転機を呼んだ。
「家庭科の先生がすごく足りなくて困っているんです。すぐにでも働いてくれませんか?」
熱心に誘われたが即答はできなかった。断ろうとも思った。教壇に立った経験はなく、家族との時間も減る不安があったからだ。
しかし、必要とされた。
“見えない存在”だったあの時とは違った。
強い要請に心動かされ、不安を抱えながらも勇気を出して決断した。
そして、藤本さんは専業主婦から“見える存在”へと大きく変わった。
その歩みは、多くの子どもや家族の未来を支えることにつながっていく。

やっぱり1番大切なのは家族|「だって、みんなのことだから」
教員生活も決して優しいものではなかった。
キャリアのスタートは、中学校の家庭科教員としての赴任だった。
自分で決めた道ではあったが、経験はなく、引継ぎを受けただけで授業に臨まなければならなかった。情報量は膨大で、直近には調理実習も迫っていた。
「家事が終わった後に勉強して授業作りしていた。」
「国語とか数学の先生は何人かいるけど、家庭科の先生って基本的に学校に1人しかいないから誰にも聞けないのさ。」
そんな中で救いだったのは、校長先生が札幌市内97校で唯一の家庭科出身の校長だったこと。
他校の先生を紹介してもらい、放課後に授業作りのポイントや指導法を学びながら少しずつ前に進んでいった。
6年間の中学校勤務ののち、小学校の特別支援学級へ。
現在は主任としてリーダーを担っている。
校種を変えた理由は、かつての職場の同僚にある。
「すごくいい人なんだけど、中々仕事を覚えられなくて…。ADHD(注意欠如・多動症)とかを知りたいと思う理由になった人物でもあるの。」
そうした人との出会いが、藤本さんを特別支援の道へと導いた。
10年間のブランクを経て社会復帰し、未経験の分野へ飛び込んだ藤本さんに聞いた。
「社会復帰への不安とか恐怖を感じている人、未経験の分野にチャレンジしようと思っている人に何か伝えることがあるとしたら?」
苦笑いをしながら「わかんない。」と言いつつも、こう答えた。
「家族やパートナーとの共通理解だと思う。もちろん健康が土台だけど、ステップアップするときに必要なのは1番一緒にいる人の理解。」
「他人事に感じてほしくない。家族だから。みんなのことだから。」
自身の体調不良をきっかけに家族の自立のために働き始めた藤本さん。
その根底には、いつだって「人を思う姿勢」があった。
人を思う気持ちは、不安や恐怖に打ち勝つ力になり、未経験の世界へと踏み出す勇気へと変わっていく。
藤本さんのリアルストーリーは、挑戦へ踏み出すアナタの背中をそっと押してくれるはずだ。

